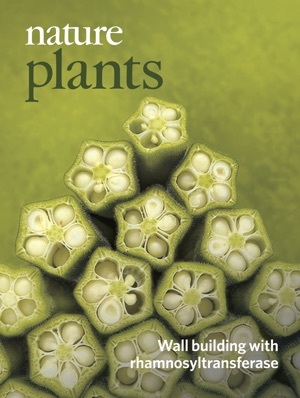石水研通信
|立命館でのセミナー
10月8日に、ロシア科学アカデミーカザン科学センターのDr. Tatyana Gorshkova、産業技術総合研究所の光田展隆先生にセミナーをしていただきました。Tatyanaは「繊維細胞」や「あて材」という特殊な植物細胞壁形成の研究に長年携わっておられます。「あて材」細胞壁の主成分の一つが石水研の研究対象のペクチンRG-Iであり、共同研究を始めるにあたって、来学していただきました。石水研のRG-Iの生合成研究とTatyanaグループのRG-Iの機能研究がマッチすると思っています。光田先生は、植物一次細胞壁合成に関わる転写因子を最近発見され、そのお話を中心に話題提供していただきました。この転写因子の制御下に石水研で探しているペクチン生合成酵素遺伝子がたくさんあるはずで、とても刺激的な発見です。石水研でのペクチン生合成酵素の発見がいろんな研究と結びついて広がり始めて、楽しい感じになって来ました。タイトなスケジュールの中のセミナーでした。Tatyana、光田先生、ありがとうございました!
 セミナー後のお食事。坂本さん、Natashaも一緒に。良い時間でした。
セミナー後のお食事。坂本さん、Natashaも一緒に。良い時間でした。
|研究成果・出版物
Takenaka, Y., Kato, K., Ogawa-Ohnishi M., Tsuruhama, K., Kajiura, H., Yagyu, K., Takeda, A., Takeda, Y., Kunieda, T., Hara-Nishimura, I., Kuroha, T., Nishitani, K., Matsubayashi, Y., and Ishimizu, T. Pectin RG-I rhamnosyltransferases represent a novel plant-specific glycosyltransferase family. Nature Plants 4, 669-676 (2018)
植物細胞は細胞壁を持っていて、ペクチンなどの多糖から構成されています。ペクチンはジャムやゼリーに日常的に使われ、漢方薬の薬効成分であることも見出されてきています。このペクチンは30~40種類くらいの糖転移酵素の作用で合成されると考えられていますが、ほとんどがまだ未解明なため、ペクチンの植物での役割がイマイチわかっていません。今回、ペクチンを合成するラムノース転移酵素遺伝子を見つけました。この酵素は糖転移酵素の一種ですが、これまでに見つかっていなかったタイプのもので、GT106という新しいファミリーであることが認定されました。この植物に特異的なGT106は非常に大きなファミリーでした。このことから、このファミリーにある多くが未解明のペクチンを合成する酵素と考えられました。そして、この遺伝子は植物の進化の過程で植物が陸上に進出した約5億年前に現れた遺伝子であることがわかり、ペクチンが植物の陸上進出に役割を果たしたと考えられました。ペクチン合成の仕組み解明に扉を開いた、と解説してくれています。大きな成果であるため、Nature Plantsという植物科学分野の高いレベルの論文が集まっている学術雑誌に掲載され、この雑誌の中でフィーチャーされ解説され、さらに2018年9月号の表紙を飾りました。いくつかの新聞やYahoo!ニュース、立命館大学のホームページなど各種メディアにも紹介されました。新着論文レビュー、月刊「化学」2018年10月号にも解説記事があります。
竹中さん(ポスドク)、加藤さん(2018年修了)、鶴浜さん(2016年修了)の貢献が大きい成果です。彼らはすごい量の実験をしました。梶浦先生、柳生さん(2018年修了)、竹田先生、武田先生の貢献もありました。名古屋大学の大西先生、松林先生、奈良先端大の國枝先生、甲南大の西村先生、東北大の黒羽先生、西谷先生には様々な協力をいただき、たいへんお世話になりました。リサーチオフィスの方々(特に中原さん)には多くのサポートをいただきました。ありがとうございました!
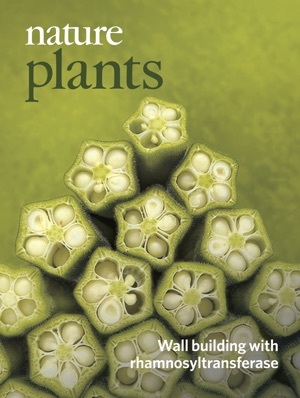 Nature Plants 2018年9月号の表紙。M1の山原さんが撮ってくれた写真が採用されました。オクラは、今回の研究対象になったペクチンラムノガラクツロナンIがたくさんあり、ネバネバしています。
Nature Plants 2018年9月号の表紙。M1の山原さんが撮ってくれた写真が採用されました。オクラは、今回の研究対象になったペクチンラムノガラクツロナンIがたくさんあり、ネバネバしています。
|研究成果・出版物
Rahman, M.Z., Tsujimori, Y., Maeda, M., Hossain, M.A., Ishimizu, T., *Kimura, Y. Molecular characterization of second tomato α1,3/4-fucosidase (α-Fuc'ase SI-2), a member of glycosyl hydrolase family 29 active toward the core α1,3-fucosyl residue in plant N-glycans. J. Biochem. 164, 53-63 (2018)
岡山大学木村吉伸先生、前田恵先生との共同研究です。植物N型糖鎖に作用するシロイヌナズナα1,3/4-フコシダーゼの発見、トマトα1,3/4-フコシダーゼα-Fuc'ase SI-1の同定、の続報。トマトゲノムには2種類のα1,3/4-フコシダーゼがあり、共に、シロイヌナズナ酵素と同様に、植物N型糖鎖のα1,3/4-フコシド結合に作用することを見出しました。
 2015年11月岡山大木村研と大山(標高1,729m)に一緒に登頂。そして一緒に論文掲載。
2015年11月岡山大木村研と大山(標高1,729m)に一緒に登頂。そして一緒に論文掲載。
|学会・シンポジウム
2018年9月10,11日に秋田県立大学で開催された応用糖質科学会大会で研究発表をしてきました。石水研の研究分野に最も近い学会であることに気づき、今回、初めて参加してきました。澱粉科学の進展、各種多糖に作用する酵素のあらゆる研究に接することができて、またこちらの研究発表に深い理解もしてくれたりで、居心地の良い学会大会でした。秋田の美味しいものを堪能しながら、こちらの研究の進展にダイレクトに関連する情報を得れたり、いろんな方と語らえたりできたのが何よりでした。


植物科学の研究が充実している秋田県立大学。食堂の名前はPlant's Cafe。懇親会ではお馴染みのなまはげ。
|学会・シンポジウム
2018年8月27日に東北大学大学院生命科学研究科の渡辺正夫先生のところで、今回Nature Plantsに発表する成果を中心にセミナーさせていただきました。共同研究の懸案の相談もあり、これからの大きめの計画の相談もありで、充実した時間を過ごさせていただきました。普段からおもてなしのホスピタリティーを施してくださり、感謝ばかりで、窮地のところを助けてくださった恩義もある先生です。その助けのおかげで一定の研究成果が出せて、今回セミナーができたのは、その恩義を少し返せた感じもして、良い機会でした。こんな感じの報告もしてくださっています。今回もお世話になり、ありがとうございました。
2018年8月30日には産業技術総合研究所の光田展隆先生のところで、セミナーさせていただきました。共同研究の密度濃い相談の時間は、光田先生のグループのとんでもない発見の成果と合間って、刺激的な時間となりました。ペクチンラムノガラクツロナンIを研究しているロシアのKazan Institute of Biochemistry and BiophysicsのNatalia Mokshinaさんと知り合う機会ともなり、濃い議論ができました。吉田さん、坂本さんにもお世話になりました。ありがとうございました!
 Natalia、石水、坂本さん。
Natalia、石水、坂本さん。