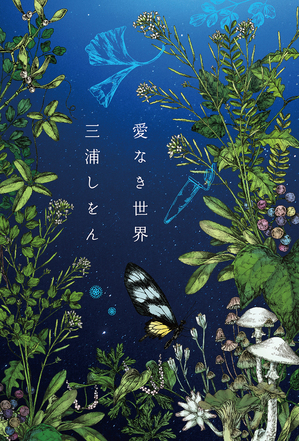石水研通信
|石水より
2018年は、石水研開設時に設定した目標「植物N型糖鎖の分解経路の解明」「植物細胞壁ペクチン生合成酵素遺伝子の同定」を達成する論文をBiochemical Journal、Nature Plantsに出せて、良い1年でした。今まで石水研に在籍した学生のがんばりによるものです。携わった学生は確実に成長したし、研究室を開設した甲斐があります。今在籍している学生の2018年は、研究を順調に進めている人とそうでない人が混在している年でした。研究が進まないと心地よくならないし、研究室で学ぶべきことを学べません。2019年は石水研に在籍している全ての人が心地よくなるようにやっていこうと思います。これが2019年の一番の目標。
昨日、大学院生時代(1992〜1997年)に指導してくださった恩師、崎山文夫先生の訃報に接しました。ご冥福をお祈りします。1960年代から1990年代にかけて、タンパク質化学分野(タンパク質合成、化学修飾による酵素研究、タンパク質工学)で地道に研究を進められた先生で、酵素研究から植物生理学研究にも切り込まれた研究を展開されました。とても生真面目な先生でした。研究初心者の私は先生の博学さに圧倒されていました。その先生から大学院生時代にいくつかのクリティカルな指導があったことを思い出して、それが今のいろんなことの進め方に影響を与えていることを思い知りました。今になってご指導に改めて感謝しているところです。
訃報に接してポカンとしているうちに、いろんなことが思い出されて、2003年に、指導していた(とても頭の良い)学生に「先生が言うことは先生が思っているより影響が大きいんやで」と指摘されたことも思い出しました。その恩師に受けた言葉、その学生に指摘された言葉がフラッシュバックしました。言葉は大きい。
立命館の学生の考え方の多様性が大きく、指導がうまくいかなくて対応に悩むことがあって、2018年後半に私が落ち込んでることがありました。落ち込むと思考停止して仕事・研究は進まないし、ほんと良くありません。研究室は学生が育っていくところ。育つ歩みはそれぞれの学生次第。落ち込むことなく気分良く接していこう。全ての学生に穏やかに気分良く対応して、慎重に継続的に愛情持って、良い言葉で、受けた指導の恩を返していく人材育成を、そして研究成果発信をしていこう。一昨日には誕生日を迎えて、若くないことはちゃんと認識しているけれど、もう48歳。2018年には、その恩師の他に、大学院生時代にお世話になった方3名の方も2018年にお亡くなりになりました。時の経過の重みを感じているところです。そう長くはない残された時間を、いろんな方に指導していただいた恩を返していくためにも、一人一人の学生が育っていくように、良い研究成果を発信できるように、過ごしていく。そんなことを思っている年始です。石水。
 2014年10月。崎山先生と。穏やかな顔。いろんな方が写っていますが、掲載にご容赦を。
2014年10月。崎山先生と。穏やかな顔。いろんな方が写っていますが、掲載にご容赦を。
12月27、28日の2日間で年末報告会を行いました。
M2は修論発表会の練習も兼ねた発表でした。先輩方の3年間の努力が感じられました。
M1は去年からの成長が感じられるというお言葉を先生からいただけました。特におざきくんは同期から見てもMVPです(笑)
B4は年末報告会後、卒業までの残り1か月でデータを少しでも増やしたいと意気込んでいました。
3回生も年末報告会に参加してくれました。内容が難しくて、どこがわからないのかすらわからない状況だったと思いますが、手を挙げて質問をしてくれた子もいました。わたしが3回生の時は年末報告会で質問をすることができなかったので、今年の3回生はすごく立派だなと感じました。
2019年度、心強いメンバーになってくれそうです!
報告会が終わってからは大掃除です!研究室、休憩室、院研、4℃室にわかれ、2017年の汚れを落とすべく掃除しました!特に床拭きはみんな必死で、ピカピカに磨き上げていました。研究室がきれいになると、気分も晴れやかになりますね!
忘年会兼3回生歓迎会は例年通り味鮮で行いました。今年1年間を振り返りながら思い出話をしたり、3回生と話したり、和気あいあいをした雰囲気で楽しめました。

12月、1月生まれの方のお誕生日のお祝いもしました。石水先生、Mint、ちゆ、まゆたろうおめでとうございます(^O^)!!
 2018年、石水先生、梶浦先生、竹中さんをはじめ、MintやM2の先輩方、同期、後輩たちにたくさんお世話になりました。皆さんありがとうございました!
2018年、石水先生、梶浦先生、竹中さんをはじめ、MintやM2の先輩方、同期、後輩たちにたくさんお世話になりました。皆さんありがとうございました!
それではよいお年を~
M1 やまはら
10/26~28に渡って開催された第12回細胞壁研究者ネットワーク定例研究会に
ミント、山原、豊田の3人で参加してきました!
細胞壁について研究している方々が集まり、それぞれ研究成果を発表しました。
他大学の生徒や先生方の発表を聞いて、その知識量やデータ量など
尊敬するところが非常に多く刺激を受けました。
今回の参加を通じて、実験に取り組む姿勢をもう一度見直す機会を得ることができたと思います!
また、発表後の懇親会では初対面の人や去年ぶりの人などと交流し、
普段の研究室や地方の話で盛り上がり親睦を深めることができました。
またどこかで会うことができたら幸いです!
今回の経験を通じて感じたことを忘れず、今後より一層頑張りたいと思います!

最後に、
せっかくの仙台ということで牛タンとずんだシェイクを
たらふく食べました。幸せでした。
M1 豊田
|石水より
「愛なき世界」(三浦しをん)という小説。シロイヌナズナの葉の形態形成の研究をしている女子大学院生本村さんと研究室近くの定食屋さんで料理人を目指す純粋な藤丸くんの周りをめぐる日常が描かれています。
シロイヌナズナ変異体の作成や遺伝子の解析をしている場面が詳細に描かれていますが、その記述が正確で驚きます。植物科学研究に興味を持っている人には勉強になると思います。三浦しをんさんの取材力と勉強量、文章力によって、わかりやすく書いてくれていて、研究の苦労もうまく描写されていて、植物研究者が読むと共感できるところが多くうれしくなるところがあります。
研究者も人間らしい心の動きは当然持っていて、恋愛もするし、趣味も持っている。そんな中で自然の秘密を解き明かしたい理学研究をする時の心情描写がうまく描かれている。読んでいて泣きそうになる場面もいくつかありました。本村さんと藤丸くんとのやりとりは絶妙で、いろんなことを思うポイントでした。逆説的なタイトルのつけ方も絶妙。ネタバレしないように詳細は省きます。
続きが読みたくなっています。大学院生が成果を出していくことで、素敵な人になっていく場面を何度も見ています。研究は人格形成にプラスに働きます。研究は、思い込みをなくして、事実を真正面から受ける能力をつけていく訓練をするものでもあり、その能力は人に対応する場面でも必要な共通なものだからと思います。三浦しをんさん、続編書いてくれないかな。本村さんの成長過程を見てみたい。
東京大学の塚谷裕一先生の研究室がモデルだとか。本郷の東大理学部の周りの地理を知っている人はより楽しめると思います。石水。
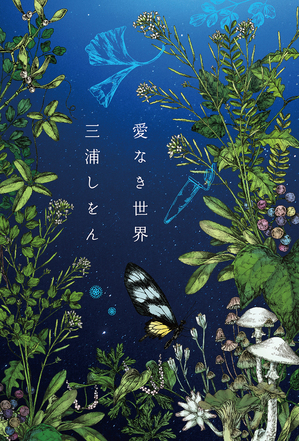
石水研は!本日も元気に!オープン卒研開催中です!!

もう石水研に来てくれた人も、まだ来れてない人も、もう一回見に行きたいなって人も皆さんお持ちしております(^O^)
何回でもお菓子とジュースのおもてなしはありますよっ☆
研究室の雰囲気を見にくるのもよし、梶浦先生や石水先生に実験内容を詳しく聞くもよし、大学院生とお話ししにくるだけでもウェルカムです!
バイオリンク7階でお持ちしております!
みんな来てね~(^O^)/

M1やまはら