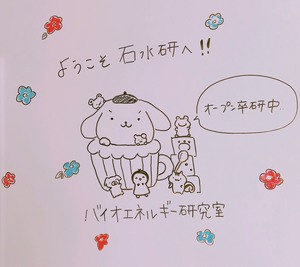日に日に秋色が濃くなる今日この頃...
個人的には大好きな季節です。
そんな季節に徒然なるままにちょっと小言を書き綴ろうかと。
この10月1日、2年半在籍していた石水研を離れ、大阪大学に移りました。
それからちょうど1ヶ月が経ちました。
自分の出身ラボだし、まぁすぐ慣れるだろう...なんて考えは甘く、1日の時間が経つのが早く、「ホンマに毎日同じ24時間かよ...」と思うスピードで日々過ぎています。
自分のペースをつかむまで、もうしばらく時間が経てば大丈夫かな、と。

ふと思い返せば、こう思うのも以前の経験が活きているのかなぁ...と。
企業に就職した時と立命館大学に助教として着任した時。
どちらも「やっていけるのか...」なんて無駄な不安を感じていたものです。
と同時に、「行動あるのみ!不安は行動が解消してくれる!!」ということも経験しました。
歳をとってしみじみ思うのが、今経験していること、努力していることは形を変えるかもしれないけど将来必ず自分の糧になるということ。
やればやるだけ"自信"という武器を自分に纏うことができるということかな。
最近、根拠のない自信をもつ人も増えてきましたが、少なくともサボっている人には絶対に得ることはできない武器だと思います。
立命館大学でも毎日楽しく自分のモチベーションを保ちつつ、サボることだけは、昨日の自分に負けないようにとは心掛けてきたつもりです。
他の研究室を含めた先生方や、学生達に恵まれたという事もそれが実践できた要因かなぁ...とも思ってます。
そのおかげで、今もなんとかやっていけてます。
ブログと言えば写真がつきものですが、ビックリするくらい立命館での写真がありません...
(飲みに行ったときに食べた料理の写真は多々あるのですが...)
せめて、昨年度の卒業式で撮った写真を載せておきます(写っていいる人、ゴメンなさい...)。

こっちにきてからも世間の狭さを感じています。
いろんなところで人の輪は繋がっています。
卒業生を含めたみんなとの輪も切れることは無いかと思います。
またどこかでお会いしましょう!
See you soon!
梶浦
10月1日からオープン卒研が始まりました!
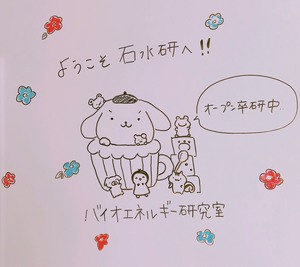
石水研にも毎日たくさんの3回生が来てくれています。
もしまだ悩んでいる3回生がいたら明るく、楽しい先輩が待ってます!
研究室って何してるの?雰囲気ってどんな感じ?1日のスケジュールは?院進か就職かどうしよう?
など質問があればすぐバイオリンク7階バイオエネルギー研究室まで!!!!

質問がなくてもうまい棒食べにきてね〜(^ ^)
B4 北川、川本、高原
|学会・シンポジウム
フランスPicardie大学のJerome Pelloux博士、Fabien Senechal博士、Josip Safran氏の来日に合わせて、東京大学(10月1日)・奈良先端科学技術大学院大学(10月3日)にて開催されたFrance-Japan Plant Cell Wall Workshop "Pectin Lovers Meeting" に参加してきました。オーガナイザーの大谷先生がつけたタイトル「Pectin Lovers Meeting」。素敵なタイトルです。東京会場では竹中が発表し、奈良会場では石水が参加しました。ペクチンのダイナミクス制御の最新知見が紹介され、今後のペクチン研究の課題について熱い議論がありました。竹中さんの発表、好評だったと聞いてます。
Jeromeグループはペクチン分解酵素をメインに、石水グループはペクチン生合成酵素をメインに研究しています。両者ともペクチンダイナミクス、ペクチンの生理機能に興味を持っていることを確認できました。短い時間で詰めて交換できる情報は交換し合いました。JeromeもFabienも穏やかな人で、こちらのたどたどしい英語を最後まで聞いてくれる真摯さ紳士さがあり、心地よい議論でした。お互いの研究内容をお互いが勉強していて、お互いにレスペクトしてるところが伝わったのも心地よさを増やしていたと思います。Josipはラーメン大好き、日本大好きな学生で楽しい人でした。
共同研究が始まりそうです。この出会い、大事にしたいと思います。オーガナイズしてくださった、大谷先生、出村先生、ありがとうございました。(石水)
 Jeromeの講演(リンク先から取った写真です)。
Jeromeの講演(リンク先から取った写真です)。
|立命館でのセミナー
9月20日、立命館大学生物資源研究センター主催のシンポジウム「バイオ研究が拓く糖質の未来」を開催しました。大阪府立大学の阪本龍司先生がPenicillium chrysogenumから単離した数々のペクチン分解酵素群について発表されました。解析できている酵素の種類、数が圧倒的で、実用的なバイオマス分解に道を拓いていることを感じました。西端豊英先生は松谷化学工業が生産している難消化性デキストリン、希少糖などの糖質化合物が至るところで使用されていることを解説してくれました。大きな需要があり、あんなとこにもこんなとこにも使用されていて、基本的な栄養素の糖質は機能性糖質としてまだ開発しがいのあるものと思いました。石水は、植物に多く含まれる糖質化合物がどうやって作られるか解明している研究を発表しました。それが植物の生理機能解明、植物の進化、今後の糖質化合物の利用に関わることを話しました。阪本先生、西端先生には、分野外の方にもわかるように講演してくださり、ありがとうございました。また研究の進展に大きな刺激を受けました。大学院生のポスター発表が20件ほどあり、良い発表練習の場になったと思います。
近隣の企業の研究者の方々にも多数ご参加いただき、産学で交流を深める機会となりました。ありがとうございました。高野さんをはじめ、立命館大学のリサーチオフィスの方々には準備・運営でたいへんお世話になりました。ありがとうございました。
立命館大学は糖質研究をしている先生方が多く、関西での拠点の一つになっています。この分野の研究成果を発信し続けれるように邁進してまいります。



|高校・中学校・小学校
9月12日、福井県の仁愛女子高等学校の2年生を迎えて、模擬講義を行いました。仁愛女子高等学校は、グローバルサイエンスコースを設けて、理系教育・英語教育にも力を入れている高校です。穏やかな雰囲気で、真面目に講義を聴いていて、反応もあり、質問もするし、とても講義をしやすかったです。レポート後にみんなが消しゴムのカスを拾い集めてゴミ箱に捨てに行っていて、ちゃんと教育を受けているように思いました。好印象でした。
「衣食住に使われる植物細胞壁の最先端研究」と題した講義・実験をしました。細胞壁成分のペクチンがゼリーに使われることを実感できる実験も行いました。各学部の特徴、普段している勉強が理系学部に進学するのにとても大事なこと、などをお話ししました。立命館大学の施設・設備が恵まれていること、研究レベルが高いこと、大学でがんばった卒業生が製薬や食品、各種業界で活躍しているということも。講義後のアンケートを読ませてもらうと、講義が響いた生徒さんがいて、講義を行った甲斐がありました。いつも思いますが、高校生の「吸収力の高さ」「キラキラした感じ」は、ほんと素敵です。ぜひぜひ受験してほしく思いました。お世話いただいた入試課の方々、仁愛の先生方、ありがとうございました!
 ピペットマンを使った操作がサマになっています
ピペットマンを使った操作がサマになっています
![]()