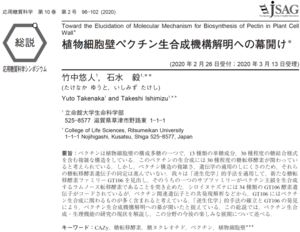石水研通信
2020年9月24日更新
今日は、この秋でドクターを卒業されたミントさんのお別れ会をしました!
アルバムや寿司トランプ、快眠アイマスクなど、たくさんプレゼントをお渡ししました。
とても喜んでいただけました(^^)!
ピザLサイズ3枚とケーキ3ホールを用意して、盛大に送り出しました!!
ですが、9人でこの量は多すぎました(笑)張り切りすぎました...。
冷蔵庫に保存して数日に分けてきちんと食べきろうと思います!!
研究室でミントさんの元気な声が聞けなくなるのは寂しいですが、
タイに帰っても元気で頑張って欲しいですね(^^)
ミントさん!結婚式には是非呼んでくださいね!♡
あっ、もちろんソーシャルディスタンスは確保しましたよ!
写真撮影時だけマスクを外しました!
2020年7月29日更新 |学会・シンポジウム
日本植物生理学会のホームページに「みんなのひろば」というページがあります。植物のふしぎに関する質問に、アドバイザーの先生方が答えているページです。小学生、大人の方、さまざまな方から寄せられる幅広い質問に答えています。植物科学の裾野を広げていることになっていて、素晴らしい学会の取り組みと思います。とても鋭い質問があったり、この部分は未解明なのかと知ることができたり、研究者にとっても有用なページになっています。
そこに「水中植物のペクチンはどうなってるの?」という質問があり、回答に協力させていただきました。 ご覧ください。
2020年7月 9日更新 |研究成果・出版物
Wachananawat, B., Kuroha, T., Takenaka, Y., Kajiura, H., Naramoto, S., Yokoyama, R., Ishizaki, K., Nishitani, K., Ishimizu, T. Diversity of pectin rhamnogalacturonan I rhamnosyltransferases in glycosyltransferase family 106. Front. Plant Sci. 11 , 997 (2020)
植物細胞壁ペクチン成分ラムノガラクツロナンI(RG-I)というドメイン構造があります。2018年にRG-I生合成酵素を見つけた ので、次はこの酵素遺伝子をノックアウトしてRG-Iができなくなる変異体植物を作り、RG-Iの植物での機能を探ろうと、研究を計画しました。ゼニゴケにはこの遺伝子が一つしかないと考えられたので、ゼニゴケを使って、この酵素遺伝子ノックアウト植物を作成しました。しかし、RG-Iはまったく減っていませんでした。想定どおりに研究が進まなかったわけです。そこで、このラムノース転移酵素遺伝子が他にもあるのではないか、との考えに至り、探したところ、他にもいっぱいゲノムにあった、シロイヌナズナには10遺伝子あった、ということがわかりました。
この論文は、想定どおりに進まなかった実験によって、研究の新たな方向性が生まれ、成果になったものです。実験が想定どおりに進まなかったことを嘆かないで、想定どおりに進まなかったということは新たな発見が隠れている、という発想を持って、研究を進めるのがいいのかなあと思います。
この論文はBussarin Wachananawatさんの学位論文の骨格になる論文です。よく頑張ったことが論文になってほんとよかったです。竹中さんのサポートは絶大でした。現在博士論文執筆中です。がんばれMint。掲載された雑誌はFrontiers in Plant Science。流行りのオープンアクセスの雑誌です。
この研究は多くの方々に協力いただきました。特に農研機構の黒羽博士、神奈川大学の西谷先生には、たいへんお世話になりました。石水研との成果の出し具合が50/50くらいの共同研究で、黒羽さんの実験技術がなければ、到達しなかった発見でした。黒羽さんの実験のうまさには驚かされました。他に、大阪大学の梶浦先生、北海道大学の楢本先生、東北大学の横山先生、神戸大学の石崎先生にもたいへんお世話になりました。ありがとうございました。
2020年7月 7日更新 |研究成果・出版物
酵素は、基質特異性によって整理されて、EC番号(酵素番号)がアサインされています。最近、7つ目の大分類項目 が出たことで話題になりました。2020年6月現在、6,519種類の酵素が登録されています。 新たな基質特異性を持つ酵素が見つかると追加されていきます。最近石水研で発見した酵素に酵素番号がつけられました。石水研からは3つ目の新規酵素登録です。
EC2.4.1.375 rhamnogalacturonan I galactosyltransferase
植物細胞壁ペクチンを合成する酵素です。現在、この酵素をコードする遺伝子を特定する研究を国際共同研究で進めています。石水研の大学院生として在籍していた松本さんが中心となってこの酵素の発見をしました。この酵素の発見は既に論文になっています。 こうして研究が世界的に使われるデータベースに残っていくのはやりがいがあることです。石水研では、まだ登録されていない酵素を4つほど研究を進めています。自分で言うのもなんですが、酵素を発見するとか、すごいなあ、と思います。酵素の発見に至るにはすごく手間暇がかかる生化学実験をしなければいけません。生化学研究は手間暇がかかるのです。それで、以前に比べると生化学の研究に関わる研究者の数が減っています。でも生化学は、基礎研究分野でも産業分野でも依然として大事な分野です。
2020年7月 6日更新 |研究成果・出版物
「応用糖質科学」という学会誌に「植物細胞壁ペクチン生合成機構解明への幕開け」と題した植物細胞壁ペクチンの生合成に関する総説を掲載してもらいました。竹中と石水の共著です。植物でペクチンがどのように合成されるか、という研究に関しては、石水研も世界的に貢献しています。石水研独自の方法論をとっているためで、それを中心に紹介しました。その方法論とは「逆生化学」的手法です。「逆生化学」という言葉は辞書等に載っておらず、一瞬ギョッとしますが、「逆遺伝学」にもじっています。酵素遺伝子の同定は通常、酵素タンパク質を精製して、そのアミノ酸配列を求め、そのアミノ酸配列をコードする遺伝子を同定するという(順)生化学的手法が一般的です。しかし、ペクチン生合成酵素は、植物での発現量が少なすぎて、この従来の(順)生化学的手法を適用できないため、研究が進展していませんでした。ここ5年くらいで、次世代シークエンサーを活用して、植物の発現遺伝子の情報について、知ることのできる情報量が莫大になってきていて、ペクチン生合成に関わる場面の遺伝子発現変動を包括的に解析することができるようになってきました。そこに目をつけました。ペクチン生合成に関わる酵素の遺伝子と予想できたものについて、リコンビナントタンパク質を作って、そこから酵素活性を検出することで、酵素遺伝子の同定に至る、従来の方法とは逆の「逆生化学的」手法でペクチン生合成酵素の同定に至ったことの解説です。ただ、この方法論は簡単ではなく、データベースから候補遺伝子を絞る技術・糖転移酵素のリコンビナントタンパク質を作る技術・糖転移酵素活性を測定する技術が必要で、他の研究室にはなかなか真似できないので、世界の名だたる大学にも負けず、立命館大学から成果を発信できています。石水研に配属される4年生に携わる研究をわかってもらうためにも執筆しました。ぜひご覧ください。
といっても、「応用糖質科学」という雑誌、学会員にしか見れなくなっているようです。学会員以外の人が見ようとすればどうすればいいんだろ?知っている人がいらっしゃいましたらご教示ください!要旨さえ見れないようなので、要旨の部分だけ貼ってみます(問題があるようでしたらすぐに削除します)。