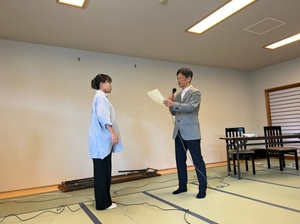石水研通信
この度は、10/16~18に白浜にて行われた第16回細胞壁研究者ネットワーク定例研究会に参加してきました。
全国から細胞壁を専門とする若手研究者が集まり研究成果を発表しました。
泊まり込みで他大学の学生や先生と親睦を深め、今後の実験のアドバイスを頂きました。同世代の学生との交流は研究のよい刺激となり、研究への活力となりました。今回築いたつながりを今後も大切にしていきたいです。
そして、M1の砂崎さんが優秀賞を受賞されました!
来年の定例会ではさらに進んだ成果を発表できるよう今後も努力したいと思います。
来年は北海道での開催ということで、おいしい海鮮も楽しみです:)
 全体集合写真
全体集合写真

豪華な会席料理
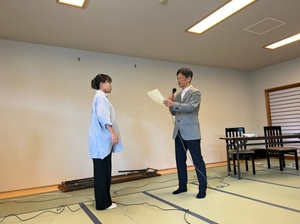 受賞された砂崎さん
受賞された砂崎さん
B4 濱田&福榮
2022年8月31日から9月2日の東京で応用糖質科学会が開催されました。今年は対面での開催となりました。私たちはスライド発表とポスター発表を行いました。私は初めての学会発表だったので少し緊張していました。ポスター発表では、学生さんや他大学の教授だけでなく企業の方々からもたくさんの質問をしていただきました。まだまだ未知なことが多いので想像でしか返答をすることができなかったのですが、とてもワクワクした表情で聞いてくださり嬉しかったです。研究を始めたばかりのB4の学生さんが研究手法について熱心に質問してくださったときは、私ももっと頑張らないといけないなと思いました。今回の学会に参加したことで、自分がやらなければならないことが明確になったのでコツコツ頑張って行きたいです。 M1 砂﨑
|高校・中学校・小学校
7月11日、三国丘高校で「三丘セミナー」を担当しました。三国丘高校のHPでも紹介されています。35年くらいの先輩として。「暮らしに関わる植物科学」と題して講演しました。石水研での植物糖鎖研究の話、植物がどのようにして硬さ柔らかさを制御しているか、植物の研究が暮らしを支えていること、それだけではなくて、自分の高校時代の話、理学部工学部農学部の違い、どうやって自分のやりたいことを見つけていくか、自分の能力を上げるために是非とも研究レベルの高い大学に進学してくれ、なんて話を提供しました。昨日受け取った感想文を読んでいると、伝えたかったことが届いていて、言葉で伝え忘れていたこともちゃんと届いていて(さすが三丘生!)、講演した甲斐がありました。3年前にも担当させていただきましたが、その時と同じようなやり甲斐を感じました。
三丘生、セミナー後の質疑応答、鋭い質問が多かったのがうれしいことでした。かわいい質問、まっすぐな質問も、質問がたくさん出たのがうれしいことでした。終了後の多くの個人質問もうれしかったです。真っ黒い水泳部の生徒さんも見つけてテンション上がりました。応援してます三丘生!
お世話してくださいました吉田先生、藤井校長先生、どうもありがとうございました!

|高校・中学校・小学校
2022年7月5日、昨年度に引き続き、堺市立西陶器小学校 6年生の「総合」で授業を担当しました。地域の人たちの生き方から学ぶ、というのがテーマの授業です。堺市出身の石水が「地球・植物のことを考える生き方」を伝えました。小学生たち、事前学習でSDGsのことを自分たちで詳しく調べてたのは良い経験になったと思います。地球上での人の生活に植物が欠かせないこと、50年後100年後の人たちのことも考えて行動していることを伝えました。「植物は人の生活にどのように役立っていますか?」「植物はかたいでしょうか?やわらかいでしょうか?」そんな質問にたくさん答えてくれました。メモをたくさん取りながら聞いていました。感じたことを言葉で表現できて、わからないことを素直に質問できていることは昨年度と同様で驚きました。小学生は目をキラキラさせて素直に聞くので、何を話すか、慎重になりました。昨日、感想文を書いてくれたのを受け取って、授業内容がちゃんと伝わっていたことがよくわかりました。植物の大事さの話が伝わっていました。植物の研究に熱中していることを伝えたことを受けて、自分も興味あることを諦めないで続けてみる、みたいな感想も多くありました。小学生、吸収力がすごいです。感想文を読んで、授業を担当させてもらった甲斐があった、としみじみしました。いい出会いになりました。
6年生担任の彦阪先生、雲岡先生、お世話してくださり、ありがとうございました。

|学会・シンポジウム
2022年6月20-21日、名古屋大学生命農学研究科(生物機能開発利用研究センター)にて集中講義してきました。
1日目は、これまでいくつかの酵素を発見してきたことを通して、どのようにして酵素を発見したのか、その経緯を伝えました。酵素を発見しようとして発見したのではなく、別課題の実験データを詳細に見てると、あれっ、というデータが出てきて、そこから酵素を発見に至るというストーリー。発見のコツのようなもの、それから転じて研究哲学にしているところも伝えました。
2日目は、石水研で同定した植物細胞壁ペクチン合成糖転移酵素とフラボノイド配糖体アピイン生合成糖転移酵素をどのようにして見つけてきたのか、という話。これまでに扱ったことのない研究手法を取り入れることで進むことがあるなど。研究材料選びの大切さなど。継続力の大事さなど。
名古屋大学の大学院生さん、質問が途絶えず、やりがいのある講義になりました。またこちらが伝えたいことが伝わったとわかるレポートが多く、今後の研究生活の決意表明したものも多く、レポートを読んでウルウルしてしまいました。とても優秀で、受講生の今後が楽しみになりました。大学院生(立命館の大学院生も含めて)は日本の希望、宝です。
佐藤ちひろ先生、北島健先生にお世話いただきました。ありがとうございました。いろいろとお話しできる時間があったのですが、ペクチン研究で謎とされているところと、ポリシアル酸研究で謎とされているところが被っているところがあり、ちょっと興奮しました。久々の対面での深い議論で楽しすぎました。スライド300枚くらいで講義しました。講義後はぐったり疲れた(これまでにない疲れ方でした、加齢のせい)のですが、とてもやりがいがありました。またどこかで集中講義を担当できればなあ、と思ったり。お声がけ、お待ちしております...。
 著名な植物の研究者も多いセンターです。
著名な植物の研究者も多いセンターです。